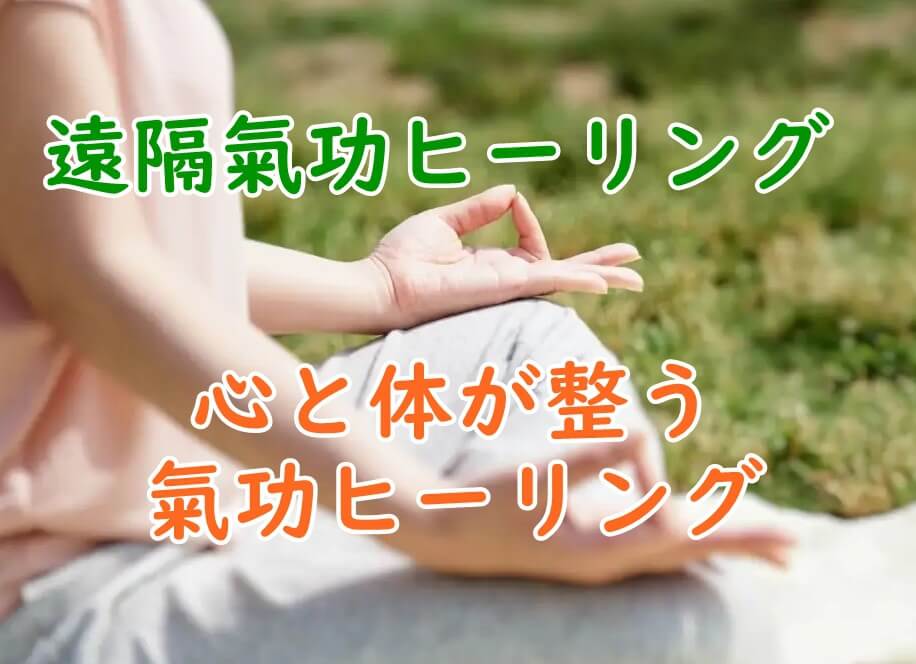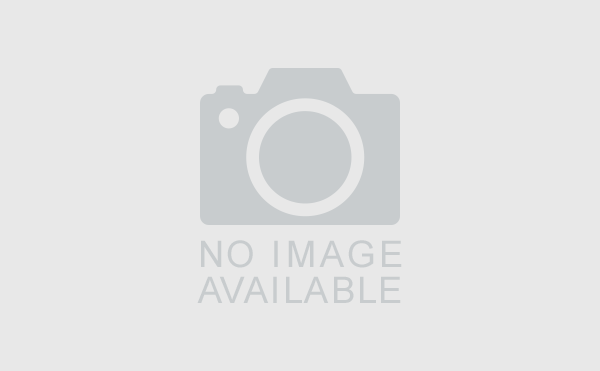呪符に込められた念は強烈に叶う 4
呪符に込められた念

呪符に込められた「念」の力
呪符において「念」は、極めて重要な役割を担っています。
「呪」という文字には「口」が含まれていますが、これは偶然ではありません。
もともと呪いとは、人の口から発せられる言葉、あるいは口に出されない言葉、つまり「念(おもい)」を意味していたのです。
また、「急急如律令」の最初の「急」の字には「口へん」が使われることがありますが、これも同様に、呪符に言葉の力が宿ることを示唆しているのです。
呪術の世界では、声に出す言葉以上に「口に出さない言葉」、つまり心の中で強く唱える言葉が重要視されています。
それこそが「念」であり、呪符の核心に存在する力です。
⸻
念に宿る感情と「鬼」の存在
ただし、呪術においての念は、単なる祈りとは異なります。
その念には、強い憎しみや恨みの感情が混ざり込んでおり、そこに「鬼」を宿らせる力があるとされているのです。
呪術とは、呪文を唱えることで念(呪力)を高め、邪鬼を退ける術です。
しかし、人は一日中呪文を唱え続けることはできません。
そのために、「呪符」が作られたのです。
⸻
人形代と呪符
呪術の中では、紙に文字や図形を書き記し、それを呪文の代わりとすることがあります。
たとえば「立春大吉日 急急如律令」という古式の呪符は、その年の安泰を願い、立春に家に貼られてきました。
本来であれば、この言葉を日々口にすることが望ましいのですが、現実的には難しいため、代わりに呪符を掲げて「念を固定化」する手段として用いるのです。
同様に「邪鬼退散 鬼急急如律令」と書かれた紙を家の壁に貼ることで、唱え続けるのと同等の効果を持たせることができます。
⸻
呪符の構成と「図形」の意味
実際の呪符では、「立春大吉日」や「邪鬼退散」といった一般語が並ぶことは少なく、
呪者たちは、念を文字や図形の形で象徴的に表すことを好みました。
いくつかの例をご紹介します。
⸻
怨敵呪殺の符
この呪符では、複数の「口」の文字が箱型に描かれるなどの構成が見られます。
この「口」は、呪いの念を象徴しています。
ここには、「地獄に落ちろ」「苦しめ」「命を絶て」といった強い憎悪の感情が込められています。
こうした呪符は、敵の家の門に貼ることで、霊的に相手を拘束し、生命力を削ぎ取る目的で用いられていました。
⸻
学業成就の符
この符には、「呂」という文字が連ねられ、線で結ばれているものが見られます。
これは「雑念を排し、努力を重ねよ」という意味が込められており、学力を向上させるための象徴とされています。
⸻
高熱封じ・発汗止めの符
「鬼」の文字だけを繰り返し記した呪符も存在します。
これは高熱や発汗を抑えるために用いられたもので、かつては「病は呪いによって起こる」と信じられていました。
汗の一滴一滴は呪いの証であると考えられ、鬼の文字を用いて、それらを封じるという意図があったのです。
なお、「鬼」の文字の数や配置は、呪者によって異なります。
しかし重要なのは、病(呪い)を力強く制圧しようとする念がこもっていることです。
⸻
その他の呪符の例
• 死霊退散の符:「尸(しかばね)」の文字を使用
• 寝言封じの符:「北口」などの文字を記す
• 寝小便封じの符:「水止」と記された符を使用
• 悪除けの符:「弓」の字を記すことで、山賊を射る意志を示す
ただし「山」「弓」などの文字も、必ずしも字義通りとは限らず、
障害物や獣、あるいは念そのものを象徴することもあります。
⸻
呪符の解釈と「念」を感じる力
呪符は、厳密な決まりのない世界です。
同じ文字が異なる意味を持ち、同じ形が異なる効果を持つ「同形異義符」も存在します。
なかには意味を完全に読み取ることができない呪符もありますが、
大切なのは、呪者が込めた強い念を感じ取ることです。
⸻
初心者と上級者、それぞれの呪符の向き合い方
呪術に不慣れな初心者であれば、
まずは「呪符に不思議な力が宿っている」と信じることが大切です。
ですが、より深い力を引き出したいのであれば、
その呪符に込められた念を読み解き、
自らの心の力と共鳴させる必要があります。
それにより、呪符は単なる紙片ではなく、
魂と感情の結晶となって、真の霊力を発揮するのです。
⸻
ご案内
護符・呪符・霊符のご依頼は、お問い合わせフォームより承っております。
また、一部の符はメルカリでもお求めいただけます。
ご自身に合ったものを、どうぞお選びくださいませ。
金運開運堂奥座敷
金運開運堂